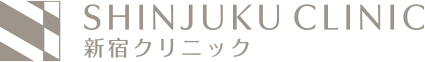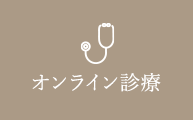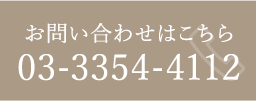当院の腫瘍内科について
 がんの治療は「三大療法」と呼ばれる手術療法、放射線療法、化学療法があります。腫瘍内科では、主に抗がん剤を使用した薬物療法を行っています。かつて抗がん剤治療は入院して行うのが一般的でしたが、現在では外来で行うことも可能となりました。
がんの治療は「三大療法」と呼ばれる手術療法、放射線療法、化学療法があります。腫瘍内科では、主に抗がん剤を使用した薬物療法を行っています。かつて抗がん剤治療は入院して行うのが一般的でしたが、現在では外来で行うことも可能となりました。
新宿クリニックの腫瘍内科では、患者様それぞれのがんの状態や抗がん剤の効果・副作用、患者様の生活の質を総合的に考慮して治療方針を決定しています。患者様の仕事や趣味と両立しながら治療を続け、患者様が自分らしく人生を過ごせるように、全力でサポートをしています。
治療についての不安や質問があれば、どうぞお気軽に当院の腫瘍内科へご相談ください。
当院の腫瘍内科の特徴
すべての領域のがんに
専門的に対応
当院では、すべての領域のがんに対して、専門的で質の高いがん診療を提供しています。他の医療機関ですでに治療を受けている方の場合、現在の主治医の先生からの紹介状が必要になります。
難治がんやステージⅣでも、
治癒をあきらめない治療を
実践
難治がんとは、転移や再発しやすいがん、あるいは5年生存率が50%以下とされるがんを指します。当院では、治癒の可能性を追求しながら、患者様お一人おひとりに適した質の高い治療を行っています。
手術前後の抗がん剤治療
にも対応
手術の前後に再発リスクを抑えるための抗がん剤治療が必要な場合でも、通院による治療が難しい患者様がおられます。当院では、現在の主治医の先生と連携をはかりながら、術前術後の抗がん剤治療を提供しています。
短い待ち時間で
ストレスなく快適に受診
患者様の貴重な時間を大切にするため、受付から治療開始までの待ち時間を極力減らせるように努めています。来院から治療開始までの待ち時間は、約30分を目安としています。
診療対象となる
主な腫瘍(がん)
肺がん
肺がんは、気管支や肺胞の細胞が正常な機能を失い、がん細胞に変化することで発生します。喫煙が肺がんの大きな原因の1つとされていますが、非喫煙者でも発症することがあります。主な症状は、咳、痰、胸痛、息切れなどです。
大腸がん
大腸がんは、大腸(結腸・直腸・肛門)の粘膜から発生するがんです。良性のポリープからがん化する場合や、正常な大腸粘膜から直接がんが発生する場合があります。飲酒や加工肉の過剰摂取が発症リスクを高めるとされており、親族に大腸がんを発症した方がいる場合も注意が必要です。主な症状は、血便や下血、下痢と便秘の繰り返し、腹痛、残便感などです。
乳がん
乳がんは、乳腺組織に発生するがんです。飲酒習慣や女性ホルモンのエストロゲンの数値が高いことが、乳がんの発症リスクを高める要因とされています。乳がんは、しこりとして自分で触れられるようになることが多く、目安としては5mmから1cm程度の大きさになると気づく場合があります。
また、乳がんはわきの下のリンパ節に転移しやすいため、リンパ節が大きくなってしこりとして触れられることがあります。、腕がむくんだり、しびれを感じたりすることがあります。
胃がん
胃がんは、胃粘膜の細胞に発生するがんで、主な原因はピロリ菌の感染とされています。主な症状には、みぞおちの痛み、胸やけ、黒色便などがあります。ただし、これらの症状は胃炎や胃潰瘍など他の病気でも見られるため、早期発見のためには定期的な検査が重要です。
肝臓がん
肝臓がんには、肝臓そのものに発生する原発性肝がんと、胃・肺・大腸など他の臓器から転移した転移性肝がんの2種類に分けられます。原発性肝がんは、主にB型・C型肝炎ウイルスが原因と発生し、アルコールの過剰摂取は肝臓がんの発症リスクを高めます。
膵臓がん
すい臓がんの多くは、膵液を運ぶ膵管の細胞から発生し、全体の90%以上を占めます。喫煙はすい臓がんの発症リスクを高める要因とされています。主な症状は、腹痛、背部痛、食欲不振、体重減少などがあります。
前立腺がん
前立腺がんは、精液の一部をつくる前立腺に発生するがんです。加齢や家族歴が発症のリスク要因とされています。主な症状には、排尿困難、頻尿、残尿感、夜間の多尿、尿意切迫、下腹部の不快感などがあります。
子宮頸がん
子宮頸がんは、子宮の入り口にあたる子宮頚部に発生するがんです。発症の多くはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が関連しており、妊娠や出産回数が多い方や喫煙習慣がある方は、子宮頸がんの発症リスクを高めます。主な症状は、不正出血、性交時の出血、おりものの異常などがあります。
腫瘍内科が対応する標準治療
当院の腫瘍内科では、以下のような治療を提供しています。患者様にとって最適な治療を行うため、必要に応じて地域の医療機関と提携し、専門性の高い治療を提供できるように努めています。
内科的治療
当院の腫瘍内科では、すべての領域のがんに対し、緩和ケアを考慮した内科的治療を行っています。他の医療機関で治療中の方やそのご家族の方にも、セカンドオピニオンのご相談に応じています。患者様の不安を少しでも解消できるように、丁寧にサポートいたします。
化学療法
化学療法は、抗がん剤を投与してがん細胞の増殖を抑えて破壊する薬物療法の1つです。全身に転移したがん細胞に効果がある全身療法です。化学療法は、がんを縮小させるために手術前に行うこともあれば、再発を予防するために手術後に行う場合もあります。また、乳がんや前立腺がんのようにホルモンが関係するがんの場合は、ホルモン療法が行われることもあります。
放射線療法
放射線療法は、がん細胞に放射線を照射することで、がん細胞を破壊する局所療法です。放射線療法には、体外から放射線を照射する外部照射と、体内に弱めの放射性物質を取り入れて体内から放射線を照射する内部照射の2種類があります。
手術
がん治療における手術は、がんを物理的に切除する治療法で、がんが発見されたときに最も一般的に行われる治療の一つです。
主に、がんの病巣とその周囲の組織、場合によってはリンパ節なども含めて摘出します。手術によってがんを完全に取り除ける可能性がある場合は「根治手術」と呼ばれます。
がんの進行度や位置、患者様の全身状態によって、開腹手術・胸腔鏡手術・腹腔鏡手術・ロボット支援手術など、さまざまな方法が選択されます。術後の再発リスクが高い場合には、補助的に抗がん剤や放射線治療を併用することもあります。
手術は、がんを直接取り除くという確実性の高い治療法である一方、体への負担も大きいため、事前に慎重な評価と説明が行われます。
腫瘍内科が対応する標準治療以外の治療
免疫療法
がん免疫療法は、患者様ご自身の免疫の力を活用してがん細胞を攻撃する、新しいタイプのがん治療法です。
私たちの体には、本来ウイルスや細菌、異常な細胞(がん細胞など)を見つけて排除する「免疫機能」が備わっています。しかし、がん細胞はこの免疫の監視を巧みにすり抜けたり、免疫の働きを弱めたりする性質を持っているため、体内で増殖してしまいます。
免疫療法は、こうしたがん細胞に対して免疫機能を再び活性化させ、がんを攻撃させることを目的としています。 近年では「免疫チェックポイント阻害薬」に代表される治療が注目されており、特定のがん種(肺がん、悪性黒色腫、腎がんなど)においては標準治療としても用いられています。この薬は、がん細胞が免疫細胞の働きを抑えるために使っているブレーキのような仕組みを解除し、再び免疫細胞ががんを攻撃できるようにするものです。
そのほか、患者様の免疫細胞を体外で活性化させてから体内に戻す「がんワクチン療法」や「樹状細胞療法」、さらには遺伝子操作でT細胞を強化する「CAR-T細胞療法」など、さまざまな免疫療法が研究・実用化されています。
免疫療法は手術・抗がん剤・放射線といった従来の治療と比べて、副作用が比較的少ないことが多く、患者様のQOL(生活の質)を保ちながら治療を継続しやすい点も特長のひとつです。ただし、すべてのがんに効果があるわけではなく、免疫療法が有効かどうかはがんの種類や進行度、個々の体質によって異なります。 当院では、患者様一人ひとりの状態に応じた適切な治療選択を行い、必要に応じて免疫療法も選択肢の一つとしてご提案しています。標準治療との併用、またはセカンドオピニオンとしてのご相談も承っていますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
ハイパーサーミア(がん温熱療法)
ハイパーサーミア(Hyperthermia)は、がん細胞を高温によって弱らせ、破壊することを目的とした治療法で、「温熱療法」や「がん熱治療」とも呼ばれています。主に体外から電磁波や超音波を利用して、がんが存在する部位を局所的に40〜43℃程度まで加温することで、がん細胞の死滅や治療感受性の向上を促します。
正常な細胞は熱への耐性が比較的高い一方、がん細胞は熱に弱く、血流や酸素供給の少ない環境下で生存していることが多いため、温熱によってダメージを受けやすいという特徴があります。この性質を利用して、ハイパーサーミアはがん細胞だけを選択的に弱らせることができます。
ハイパーサーミア単独でもがん治療効果が期待されますが、一般的には抗がん剤治療や放射線治療と併用することで、相乗的な効果を発揮します。温熱によって血流が促進され、薬剤や酸素の供給が改善するため、化学療法や放射線の効果が高まりやすくなるのです。
これにより、がんの縮小や再発抑制が期待されます。
主な適応がんとしては、再発乳がん、肝臓がん、膀胱がん、前立腺がん、子宮頸がんなどがありますが、体への負担が少なく、治療中の痛みもほとんどないため、高齢の方や持病のある方にも選択肢として検討されるケースがあります。
副作用は比較的軽微で、治療部位の軽度なやけどや赤み、腫れなどが起こることがありますが、多くは一時的なものであり、重篤な副作用は稀です。
遺伝子治療
がん治療における遺伝子治療は、がん細胞の発生や進行に関与する遺伝子の異常を標的として、がんの制御や治癒を目指す先進的な治療法です。従来の抗がん剤や放射線治療は、正常な細胞にも影響を与える可能性がありましたが、遺伝子治療はがんの根本原因にアプローチすることで、より選択的かつ個別化された治療を可能にします。
がんの多くは、細胞の増殖・分裂・死に関与する遺伝子の異常によって発生します。代表的なものが「P53」と呼ばれるがん抑制遺伝子です。P53は「ゲノムの番人」とも呼ばれ、細胞に異常が生じた際に増殖を止めたり、修復不能な場合には細胞死(アポトーシス)を誘導したりして、がん化を防ぐ働きを担っています。しかし、がん細胞の多くではこのP53遺伝子が変異して機能を失っており、異常な細胞が分裂を続けてしまう原因の一つになっています。
遺伝子治療では、P53の機能を回復させるために、正常なP53遺伝子をがん細胞に導入する方法が研究されています。これにより、がん細胞に本来の抑制機能を取り戻させ、自然な細胞死を誘導することが可能になります。
一方、「CDC6(Cell Division Cycle 6)」は、細胞分裂の初期段階に必要なタンパク質であり、正常な細胞では厳密に制御されています。しかし、がん細胞ではCDC6が過剰に発現し、細胞分裂が異常に活性化されることでがんの増殖を促進することが知られています。最近の研究では、CDC6を制御することでがん細胞の増殖を抑制したり、免疫反応を誘導する可能性が示唆されており、がん遺伝子治療の新たな標的として注目されています。
このように、がん遺伝子治療はP53やCDC6といったがん関連遺伝子に直接働きかけることで、従来の治療とは異なるメカニズムでがんを抑えるアプローチです。現在は臨床研究段階のものも多く、保険適用外の治療となる場合もありますが、個別化医療が進む中で、将来的にはより多くのがん種に応用されることが期待されています。
食事療法
がん治療における食事療法は、栄養バランスの取れた食事を通じて、体力の維持や治療効果の向上、副作用の軽減を図ることを目的とした重要なサポート療法のひとつです。がん治療中は、抗がん剤や放射線、手術などによる体への負担が大きく、食欲不振や味覚の変化、吐き気、下痢、口内炎などの副作用によって食事がとりづらくなることがあります。このような状態でも、適切な栄養を摂取することは、免疫力の維持や合併症の予防、回復力の促進に大きく貢献します。
食事療法では、タンパク質、エネルギー(カロリー)、ビタミン、ミネラルなど、必要な栄養素を無理なく摂取できるように工夫します。とくに筋肉量の維持に関わるタンパク質や、治療による体力消耗を補うエネルギー源は欠かせません。食欲が低下している場合には、少量でも栄養価の高い食品を選ぶことや、食べやすい調理方法(柔らかい・冷たい・匂いの少ない)を工夫することがポイントとなります。
また、がんの種類や治療方法によって推奨される食事内容は異なります。たとえば消化器がんの術後や、口腔・咽頭がんなどで咀嚼や嚥下に支障がある場合には、形状を工夫した食事や、流動食、栄養補助食品を取り入れることもあります。一方で、過度な糖質制限や特定の食品に偏った「がんに効く」とされる極端な食事法には注意が必要です。科学的根拠に基づかない方法は、かえって健康を損なう恐れがあります。
オブジーボ
オプジーボ(一般名:ニボルマブ)は、がん免疫療法の一種である「免疫チェックポイント阻害薬」に分類される注射薬です。患者様の免疫機能を活性化し、がん細胞に対する攻撃力を高めることで、がんの進行を抑える効果が期待されます。日本では2014年に悪性黒色腫(メラノーマ)に対して承認されて以降、肺がん、腎細胞がん、胃がん、頭頸部がん、食道がん、大腸がん、膀胱がんなど、さまざまながん種に適応が拡大されてきました。がん細胞は、免疫細胞の働きを抑える「PD-L1」というたんぱく質を表面に出し、免疫による攻撃から逃れようとします。オプジーボは、このPD-L1と結合する免疫細胞側の受容体「PD-1」に作用し、その結びつきを阻害します。これにより、がん細胞に対する免疫細胞(T細胞)の働きが再び活性化され、体内の免疫ががんを攻撃できるようになるのです。
従来の抗がん剤や分子標的薬とは異なり、オプジーボはがん細胞そのものではなく「患者様の免疫機構」に作用する点が大きな特長です。そのため、副作用の種類や出方も異なり、免疫が正常な組織を攻撃してしまう「免疫関連有害事象(irAE)」と呼ばれる副作用が起こることがあります。代表的なものには、肺炎、腸炎、肝機能障害、皮膚炎、内分泌異常(甲状腺機能異常や副腎機能低下など)などがあります。早期発見と適切な対応により重症化を防ぐことができるため、治療中は定期的な検査や症状の変化に注意が必要です。
オプジーボは単独で使用される場合もありますが、近年では他の免疫療法薬(例:ヤーボイ)や化学療法との併用療法も多く行われています。治療の効果が現れるまでに時間がかかることもありますが、持続的な効果が期待できるケースもあり、一部の患者様では長期生存も報告されています。
腫瘍内科の受診の流れ

1ご予約
Webサイトまたはお電話でご予約をお取りください。
初診の方は受付で保険証をご提示ください。再診の方も月初めには保険証の確認が必要なため、忘れずにお持ちください。
紹介状や画像データをお持ちの方は、ご持参いただき受付でお渡しください。

2診察
問診表をもとに医師が診察を行います。悩んでいることやお困りのことがあれば、遠慮なくご相談ください。
3精密検査
診察の内容を踏まえて、必要に応じて血液検査、画像検査、生検検査などを行います。

4治療方針を説明
診察や検査で判断された結果をお伝えし、これからの治療方針を決定します。
気になることやわかりにくい点があれば、遠慮なくご質問ください。

5治療開始
一人ひとりにあった治療法をご提案します。治療によって異なりますが、基本的には、診察から約2~4週間後から治療を開始します。スケジュールについては、患者様とご相談の上、決定いたします。